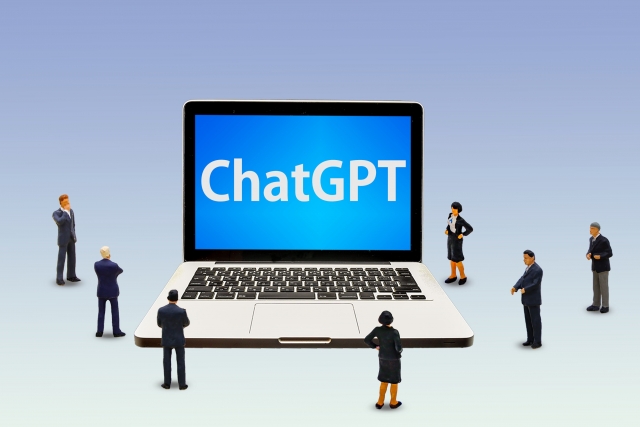今日は、最近僕が体験した、生成AIとの効果的な付き合い方について、ちょっとお話をしたいと思います。というのも、先日、生成AIとの付き合い方について、まさに目から鱗が落ちるような体験をしたんです。その内容を皆さんにも共有できればと思って文章にしてみました。
問いかけ続けるAI。対話の先に、無限の可能性が広がる。
以前の僕は、生成AIって正直、検索エンジンのちょっと進化したバージョンみたいなもんだと思ってたんですね。つまり、キーワードを正確に入力したら、それに対する答えがポンって出てくる、みたいな。だから、「AIに聞けば、何でも正解がわかる」みたいな、ちょっと機械的な捉え方をしてたんですね。
でも、先日参加したイベントでの講演会が、もうね、僕のその考え方を完全にひっくり返してくれたんですよ。
講演会では実際に生成AIを使って色々やってみたんですけど、その中でAIとのやり取りは、単なる質問と回答じゃなくて「言葉のキャッチボール」つまり「ラリー」をすることが、めちゃくちゃ重要だってことがわかったんです。
これはもう、目から鱗が落ちるどころの話じゃなかったですね。衝撃的でしたね。
その講演会でまず驚いたのが音声入力でAIに指示してたんですよ。
それも、完璧な日本語じゃなくても大丈夫で。例えば、ちょっと言葉が途切れてたり、文法が多少おかしくても、AIはちゃんと僕たちの言いたいことを理解しようとしてくれるんです。そして、その理解に基づいて、AIがアウトプットを出してくれる。
最初は、「え?これで伝わるの?」って半信半疑だったんですけど、実際にやってみると、ちゃんとAIが反応するんですよ。で、さらに驚いたのが、そのアウトプットに対して、講演会の方が、「いやいや、そうじゃないんだよな。もっと、こういう雰囲気で、こういう感じで、こういうのが欲しいんだよ」って、まるで人と話すみたいに、フランクにフィードバックしていくんです。
しかも、そのフィードバックを受けて、AIがまたすぐに新しいアウトプットを出す。そのやり取りが、まるで人と人が言葉でコミュニケーションをとっているみたいで、見ていて、「え、AIって、こんなこともできるの?!」って、本当に衝撃でしたね。
AIがまるで、僕たちの言葉のニュアンスまで理解しようとしてるみたいな、そんな感じがして、もう、ただただ驚くばかりでした。
AIは思考の壁打ち相手。言葉のラリーで潜在能力を解き放つ。
それで講演会での体験があまりにも衝撃的だったんで、僕も実際に生成AIとの「言葉のラリー」を意識して使うようになったんですよ。
そしたら、これがもう、想像以上に効果があったんです!
例えば、先日どうしても仕事のモードになれない日があったんですけど、そんな時に試しに生成AIに、「今の状況を打破するには、どうしたら良いと思う?」って、軽い気持ちで質問してみたんです。
今までの僕だったら、質問してAIの回答を「ふーん、なるほどね」って受け止めて終わりだったんですが、今回は、「それって、具体的にどういうこと?」とか、「その考え方だと、こういうリスクもあるんじゃない?」とか、AIの回答に対して、さらに質問を重ねたり、別の角度から問いかけてみたり、色々試してみたんです。
そうしたら、まるで誰かと壁打ちをしているみたいに、問題に対する理解がどんどん深まっていくのがわかったんです。AIと対話していく中で、自分の考えが整理されて、「あ、そういうことか!」って、最終的には、かなり納得のいく形にたどり着くことができたんです。
これ、本当に新しい発見でしたね。今まで、生成AIって、ただの道具だと思ってたけど、使い方次第で、こんなにも自分の思考を助けてくれるパートナーになるんだって、心から実感しました。
多分ね、今までの僕の生成AIの使い方って単に質問して、答えをもらうだけっていう、ちょっと一方通行な感じだったんだと思うんですよ。
だから、今回みたいに「言葉のラリー」を意識して、AIと対話を重ねながら、一緒に答えを探していくっていう使い方が、今までとは全く違った、新しい体験だったので、すごく新鮮だったんだと思います。
でも、それ以上に、この「言葉のラリー」を意識して使ってみて、「あ、これだ!」って確信したんです。生成AIのポテンシャルを最大限に引き出すためには、こんな使い方が良いって。
これまでの使い方だと、AIはただの便利なツールでしかなかったけど、「言葉のラリー」を意識することで、AIが、自分自身の思考をサポートしてくれる、頼れるパートナーになる。そう考えると、生成AIの価値って、本当に格段に上がるんじゃないかな、って思いました。
AIは文章作成の救世主。プロンプトと対話を使い分けで効率UP!
もちろんプロンプト、つまりAIに対する指示文も、全く使えないってわけじゃないんですよ。
例えば、定型的な文章を作ったり、似たようなアイデアをたくさん出したい時には、プロンプトは非常に役立ちます。「〇〇について10個アイデアを出して」とか、「〇〇を〇〇文字で説明して」みたいに、具体的な指示をすれば、AIはそれなりの答えを返してくれます。
でもね、複雑な要求とか、「これだ!」っていう、まさにピンポイントな答えが欲しい時って、プロンプトだけでは、なかなか難しいんですよね。
そういう時は、AIと対話形式で、「こういうイメージなんだけど、どうかな?」「もう少し、こういう要素も加えてくれると嬉しいんだけど」みたいに、コミュニケーションを取った方がより自然で効率的な、そして納得のいく答えが、見つかることが多いんです。
だから、プロンプトと対話形式、どっちが良いとか悪いとかじゃなくて、状況に応じて、上手く使い分けることが、めちゃくちゃ大切だと思うんですよね。
生成AIを積極的に活用することで、僕たちの仕事や日常生活って、本当に大きく変わると思うんですよ。
例えば、文章を書くのが苦手だって人、いますよね?そういう人にとって、生成AIはまさに救世主になり得るんです。ブログ記事とか、ホームページの文章作成とか、「うわ、どうしよう…」って、頭を抱えちゃうような作業も、生成AIに任せれば、大幅な時間短縮と効率化が期待できます。
僕もそうなんですが、記事の構成を考えたり文章を肉付けするのって、結構時間もかかるし、エネルギーも使うんですよね。でも、生成AIに、「こういう内容の記事を書きたいんだけど、構成案を作ってくれない?」「この部分の文章をもう少し分かりやすくして」ってお願いすると、AIは本当にあっという間に、「え、もうできたの?」ってくらい、高品質なアウトプットを出してくれるんです。
あとは、そのアウトプットを参考にしながら細かい部分を自分で手直しするだけで、クオリティの高いコンテンツを、驚くほど効率的に作成できるんです。これ、本当にすごいことだと思いませんか?
AIは助っ人、最終判断は人間。検証を忘れず、AIと共創しよう。
それから、生成AIを使う上で絶対に忘れてはいけないのが、生成AIにも限界があるっていうことなんです。
AIが出力する情報って、「はい、これが100%正しいです!」って、保証されているわけじゃないんですよ。時には、事実と違うことを、平気でそれっぽく言ってくることだってあるんです。
例えば、歴史的な出来事を聞いた時に、「それは違うんじゃない?」っていう、間違った情報を出してくることだってあります。だから、AIが出力した情報を、「AIが言ってるから、絶対に正しいんだ!」って、鵜呑みにしちゃ絶対にダメなんです。
必ず、自分で調べて、確認する、つまり、検証するっていうことが、めちゃくちゃ大切なんです。生成AIは、あくまでも僕たちの活動を支援する「頼もしい助っ人」であって、最終的な判断を下すのは、常に「僕たち人間」なんです。このことを、絶対に忘れないでほしいと思います。
百聞は一見に如かず。まずはAIに触れて、自分だけの最適解を見つけよう。
今の世の中、生成AIを使いこなせる人と、そうでない人の差が、どんどん広がってきていると僕はひしひしと感じてるんですよね。生成AIを積極的に活用することで、僕たちの仕事の効率や生産性って、本当に劇的に向上する可能性を秘めているんです。
でも、「まあ、別に今すぐ使わなくてもいいかな…」なんて、先送りにしていると、知らない間に、周りの人にどんどん差をつけられてしまうかもしれない。これは、ちょっと怖い現実ですよね。
だから、まずは、「百聞は一見に如かず」じゃないですけど、難しく考えずに、まずは実際に触ってみることから始めてほしいんです。
色々な場面で生成AIを試してみたり、色々な人に聞いてみたりしながら、「あ、この使い方、自分に合ってるな」とか、「この部分は、AIに任せると効率が良いな」って、自分にとって最適な活用方法を、見つけていくことが、めちゃくちゃ大切だと思うんですよね。
AIって、使いこなせる人とそうじゃない人で、これから大きな差が生まれると思うから、まずは一歩踏み出す勇気を持ってほしいです。
AIは最高の相棒。言葉のラリーで共に成長し、答えを創り出す。
僕が今回の体験を通して、一番強く感じたのは、生成AIを使いこなす上で最も重要なのは、単なる便利な道具としてではなく、対話を通して、一緒に最高の答えを導き出してくれる、心強いパートナーとして捉えることだってこ事ですかね。
AIとのやり取りって、ただ質問して、答えをもらうだけの、一方通行なものではないんですよ。そうじゃなくて、質問と回答を何度も繰り返す「ラリー」、つまり、キャッチボールをすることで、お互いの理解を深め、より良い答えにたどり着けると思うんです。
AIって、「指示されたことをただやる機械」ではなく、「一緒に考えることを楽しめる、頼れる相棒」なんですよね。
だから、生成AIを「対話を通じて、共に成長していくパートナー」として、捉えるほうが愛着が湧くというか。親しみを持って接することができるんじゃないかなと思いました。